『美味しい革命』 アリス・ウォーター
プロローグ・・・オープン第一夜
1971年8月28日 当時アリス27歳にカリフォルニア州バークレー市シャタック通りにある
古びた一軒家にOPENした小さなレストラン、それが”シェパニーズ”
(今では世界でもっとも予約の取れないレストランと言われている)
誰もが気軽に立ち寄れる集会所のようなところにしようと心に決めていた。
その晩のメニューは1種類のみ
・パテのパイ皮包み
・鴨肉のオリーブ煮
・あんずのタルト
・コーヒー 3ドル95セント
ワインはモンダヴィのフュメ・ブランとガメイ、グラスの注文には上等なソーテルヌ、シャトー・スデュイローが用意されていた。
プロとしてレストランで働いたことのある人は1人もいなかった。
キッチンでは鴨が煮込み続けられているがなかなか柔らかくならない
前菜が出てから、最初の鴨料理が出るまで、たっぷり1時間はかかった。
ダイニングルームはしびれを切らしだんだん静かになっていた
全員に鴨料理が出そろうまでに優に2時間はかかった、ずぶの素人がみんな必死でやった
「それが私たちのやり方、やりながらどうやっていくかみんなで考えて決めていく、考えてみればクレイジーだった。」とアリス
無我夢中だったが、120人分のお料理がサーブされた。
その内、数名からはお代を頂いたか、だれも覚えていない。
みんな疲れ果てていたけど、ハッピーだった。
それから35年後2006年アメリカで1番名高いレストランと言っても過言ではない。
グルメ達の愛読誌『グルメ』が5年に一度発表する全国レストランランキングで、
ナンバー1になった。
やりながら考えて決めてきた小さくて向こう見ずな仲間がどうしてそんなアイコンとなる事ができたのか。
シェパニーズはレストランというよりもっとスケールの大きいひとつの事業だ。
アリス・ウォータースは多くのアメリカ人の食習慣を変え、食べ物に対する考え方を変えてきた。オーガニック農法で育てた
一番新鮮な旬の食材を地元で調達するべきだ、という彼女の考え方は、今やアメリカの一流レストランと多くの家庭料理人たちの鉄則となっている。
第1章・・・パリのスープ
1944年4月28日4人娘の2番目として生まれたアリス。
幼い頃の記憶は、家庭菜園で遊んでいた時から始まっている。アリスの父は視力が弱かったので、
兵士として第2次世界大戦に参戦することは出来なかった。
その代わりに与えられた役目は戦時中の食糧確保のために奨励された“勝利の菜園”をつくる事だった。
アリスは自然の中のいろいろな匂いを覚えている。ハックルベリー公園の野原を転げまわったときの刈ったばかりの草の匂い、
春になってレンギョウの垣根やライラックとその下に咲いていたスズランの花の匂い、
少女時代の思い出から感覚が極端に鋭敏だったことが窺える。そのうちアリスは平凡な女の子から
カぺジオのピンクのハイヒールで決めたお洒落なティーンエージャーへと脱皮した。暗闇で本気でキスをする位まで成長していった。
ハイスクールではもっぱらpartyと男の子の日々だった。
アリスはカリフォルニア大学のサンタ・バーバラ校へ進学した。
学生時代の思い出と言えば、蝶のように舞いバラのごとく着飾った連日のparty、
そして途方もない量の酒。彼女は頭はよかったが、このままでは頭が空っぽのパーティーガールになってしまう、
そんな時同じ高校出身のエレノアが一緒にバークレー校に転校しないかと誘ってきた。そしてもう一人の友達サラと3人で
転校願いを提出した。
何かが上手くいかなくなった時、どこからともなく救いの手が差し伸べられる。
その出来事が彼女の人生を大きく変えられるきっかけとなる。
ときどき彼女は
「私はあまり目標をもって生きるタイプではなく、どちらかというと人から言われて行動を起こすほうなのよ」
その秋、サラがパリのソルボンヌ大学留学のパンフレットを持ってきた、悪くないなと思った。
アリスはそれまで外国に行ったことがなかった。そのころのアリスは食べ物に関してよく知らなかった。
ただフランス語が話せるようになったらいいなと思ってはいた。
それから、フランス人男性にも興味があった。
第2章・・60年代らしい時期
アリスの美意識と政治的信念は、ロマン主義のヨーロッパ文化を学ぶことで実を結んだ。
彼女は自分の思い通りにことが進まないと気が済まない人だったし、またそれをするエネルギーと強さをもっていた。
重たいマットレスを2人がかりで運ぼうとしていると、アリスは1人で背中に担いで、さっさと階段をあがってしまう。
彼女は留まるところを知らいない人で、立ち止まってあれこれとことん考えるような人ではない。
アリスも、そして多くの同級生も、それまでとは違う新しい世界の到来が近づいていると予感していた。
それは、彼女たち自らが先駆者となって開拓する、新しい社会だ。
アリスのようにメニューを考えるという事に時間をかけてきた人は、これとこれは何でつながっているのか、だんだん
わかってくるらしい。
繋がっている何かに注意を払うことが、この持続可能性という思想として花開いた。
人間のあらゆる営為はわれわれを包むより大きな環境の一部であって、資源は自然の経過の中で再生されるものであるから、
永遠に存続できるという考え方だ。
第3章・・モンテッソーリと夢
アリスはいつか自分のレストランを開きたいという夢を持ってはいた。
その頃はまだファンタジーの域を出ていなかった。
ディヴィットとアリスは「サンフランシスコ・エキスプレス・タイムズ」という志向をもった週刊誌上で「アリスのレストラン」
というタイトルの料理コラムを共同で書き始めた。
毎回アリスの好きな料理のレシピを書き、それをディヴィットが挿絵付きの版画に仕上げた。1970年にディヴィットはそれらをまとめて
「額縁に入れたい30のレシピ」という限定本にまとめている。
アリスが1番好きだった料理方法は市場でよさそうな食材を買ってきてそれを活かして調理することだった。彼女はフランスの人たちがそれをしているのを自分の目で
見てきた。
フランスの大都市にある、ミシュランの星のついたような格式高いレストランでは、そんな即興的アプローチはプロの仕事ではない、当然のように考えられていた。
味で勝負するレストランならば、来る日も来る日も同じように、均一で質の高い料理を出せるという事になっている。
アリスの好みに合うのは中程度あるいは小さな規模のレストランなのだ。
「新鮮な食材!これだは、もちろん料理にはテクニックは必要よ、いい食材からはじめなきゃ美味しい料理はできないわ」
だが彼女は本当にお金がなかった。どうやってお金をつくればいいのかもわからなかった。
アリスの姉の友人バーバラはモンテッソーリ式幼児教育の教師で、アリスに助手になるよう勧めた。アリスはすぐに夢中になった。
モンテッソーリの教育は、すべて感覚を通じて世界と接触していく方法で「手は心の道具」という考え方だった。
モンテッソーリの教育の訓練を受けるにはロンドンの国際モンテッソーリ・センターが1番よいとされていた。
アリスはそこで教師のライセンスと取ることになった。
モンテッソーリのいいところは、どんな子供にも何か得意なものがあると考え、
それが何なのかを見つけその子がそれに情熱を注げるように扉を開けてあげるところだ。
それが彼らに自信を与え、生きる情熱を与える。
その冬、アリスはディヴィットと別れることになった、その後も良き友人としての関係は保っていた。
それから、時が経って
アリスは映画館の若いマネージャートムと出会い恋に落ちた。
アリスは1970年の終わりまでには自分の夢が実現しそうだという事を実感してきた。
レストランの名前を映画の登場人物の名前から「シェ・パニーズ」に決定した。
彼女がくだしたもっとも重大な決断は、夕食メニューを1つのコースだけに絞ったこと。
誰かの家に夕食に招かれたみたいにしたかった。コースのメニューは毎晩かわり
週7日、定休日なしの営業。
1971年8月、アリスはスタッフを雇いはじめた。経験は一切不問。
アリスはシェパニーズでの仕事に向いているのがどんな人物であるか、明確な人物像を持っていた。
多くの応募者の中から「この人はきっとシェパニーズのことがわかるはずだわ」
というアリスのカンで選考した結果、驚くほど知的レベルの高い人間が集まった。
これだけの頭脳が集まれば、知識が欠けていたとしても想像力で補えるだろうと思った。
経験が足りない部分は、人海戦術で何とかするつもりだった。
1971年8月27日、その日は明け方から内装工事と塗装が始まり、夜中まで続けられた。半ばパニック状態で工事は続けられた。
ぐつぐつ煮ているスープの芳香が、おがくずやペンキの強いにおいに混じり合っていた。
6時が近づいても走り回る料理人、特に不安が顔にありありと表れたアリスを尻目に大工たちはまだ棚に釘を打っていた。
第4章 いかにもバークレーらしいところ
レストランがオープンして数字は無事過ぎた、アリスはハッピーではあったが満足してはいなかった。
アリスのビジョンではシェパニーズは一流レストランにはならないが、質の面では絶対に妥協しないつもりだった。
「手抜きは絶対になしね」彼女は誰に対しても念を押した。
アリスが仕入れたがる食料品は値が張った。
「フランスで食べたような料理を求めていたの、わたしにとっては探求の旅というところかしら」
彼女はビジネスについて何も知らなかったし、どうでもよかった。
彼女は値段など気にせず買ってきた。シェパニーズの財政危機は近い将来解決できそうにもないように見えた。
しかし、レストランとしては次第に安定してきた。アリスとしては値段を安くしたのはやまやまだったが、
何といっても彼女の根っからの高級嗜好と、すべてにおいてベストでそろえるやり方では、
そういつも大判振る舞いというわけにはいかなかった。
誰かが裏庭で取れたばかりのラディッシュだとか、まだ露に濡れている泥がついたままの新鮮な野菜のかごを持って
シェパニーズにやってきたとすると、それをお金で買うのではなくお返しにディナーを差し上げる、こうゆうやり方はバークレーの人々は、
きわめてバークレーらしい、やり方だという。
スタッフが勤務中にワインを飲んでしまうこともよくあった。
1972年レストランの営業開始から1年もたたない時に誰かが損失額を計算したら3万ドルのワインの行方が分からなくなっていた。
シェパニーズの歴史の中でもっとも不可思議なのは、こんなめちゃくちゃな経営理念と意図的な採算度外視の状況が何年も続いたにも
関わらずレストランの評判はどんどん上がって言った事だ、ビジネスとして利益を出すには30年もかかったが。
まっしぐらだったアリスの情熱は次第に規律正しさに変っていった。
リンゼイ・シェアがその模範をつくった。彼女は常に落ち着いていて、聡明で几帳面な女性だった。きわめつけな繊細な味覚を
持ち合わせたリンゼイとアリスは、言葉で表現しなくてもお互いの感覚の疎通ができた。リンゼイは質素な農家暮らしの倹約家でもあった。
リンゼイはアリスと同じくらいスーパーから買う食材の質の低さに頭を悩ませていた。
当時、バークレーにあった高級食料品専門店をうろつきまわっただけでなく、直接産地にいって収集までした。
清流が流れる小川でクレソンを摘んだり、友人の家庭菜園からハーブをもらったりもしました。
こんなことを本当にやったレストランがアメリカに当時あっただろうか、地元の匂いや地方の感触を料理に取り込んだのだ。
トムはシェパニーズのようなレストランは他にはないという事を理解していた。
もっと広く知られるべきだと信じていた。
それからしばらくして、トムは名声高いパシフィック・フィルム・アーカイブのディレクターとなった。
ほとんど毎週有名な映画監督がトムを訪ねてきた、それに有名な男優、女優もいつも彼らをトムはシェパニーズに招待した。
この世界的著名人たちはアメリカで滅多にない、なにかまったく新しいことがシェパニーズで起こることを感じ取っていた。
第5章・・貴公子ジェレマイア
シェパニーズに新しいシェフがやってきた、そのシェフ「ジェレマイア」がシェパニーズを“かなりいいレストラン”から
“真に偉大なレストラン”へと変身させた。
彼はハーバード出身だった。
彼のアシスタントとなったのは、髭もじゃでちりちりパーマがかかったような髪をした元ヒッピー、ウィリー・ビショップだった。
彼はアーティストでもあった。
ジェレマイアは文化改革計画をただちに開始した。音楽も変え、2階のカフェも少しの改造でレストランにした。
次第にシェパニーズは海岸通りの心地よい居酒屋ムードを抜け出し、開店後2年足らずで、給料日から給料日をつなぐのがやっとで、どの面にも素人さが残っていたが、
知らず知らずのうちに大レストランの風格を持ち始めていた。
ジェレマイアもアリスもますます、いい食材を探し回るようになった。
アメリカのほとんどの地域では良質な材料は手に入る見込みは少なくなる一方だった。家族単位の農家はどんどん姿を消していった。
簡単で美味しい家庭料理をする家族経営の小さなレストランはマクドナルドを建てるためにどんどん潰れていった。
大量購入と大規模マーケティングでチェーン店の出現はハンバーガー、フライドチキン、ピッツァの範囲を大きく超えて広がっていた。
こういったレストランでは使う砂糖と脂の量は家庭の2倍以上だった。
アメリカの肥満問題の夜明けだった。アリスはただ頭を抱えているだけだった。
第6章・・これが最後のバースデー?
アリスは昔から地元産の食材を好んだが、ジェレマイアの凝った料理をつくるには、遠隔地からの食材も必要だった。
シンプルに料理するようになってアリスとジェレマイアは地元の食材の質が向上しているのに気付いた。
キッチンから出てくる料理は地元産、レストランから数マイル以内で栽培された果物や野菜をどんどん使うようになった。
1976年夏から、ファーマーズマーケットの農産物がシェパニーズの基本の食材となっただけでなく、基本の考え方になった。
レストランはその精神を取り戻していたかもしれないが、アリスは取り戻していなかった。
新しい客は、勝手にやめると決めたら、キャンセルの電話もなく店に現れない。私たちの存在は大きい。
もっと悪いのは料理が無駄になり、ごみ箱に捨てられた。
ジェレマイアが辞める日は近づいていた。
激動の4年間にアリストジェレマイアが作りあげたものは、野心的にしてシンプルで、世界的な広がりをもちつつも、同時に家庭的、
クラシカルでしかも現代的というユニークなコンビネーションでもあった。こういう特質はシェパニーズに受け継がれている。
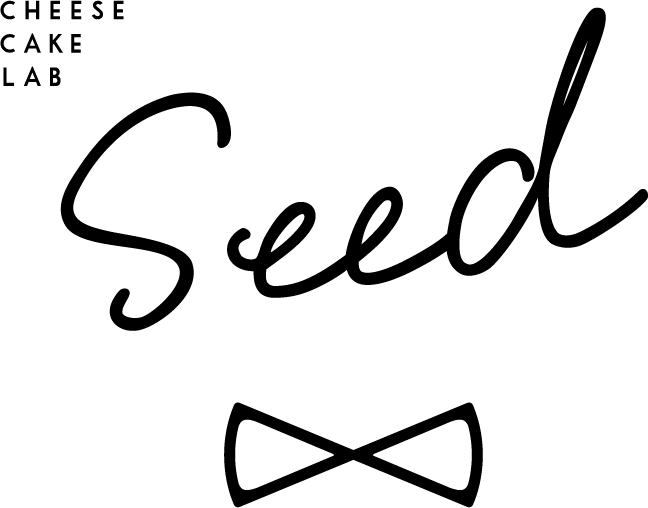










この記事へのコメントはこちら